
特別展「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」
仏教伝来以前の古い日本では、神は山、滝、岩や樹木等に宿ると信じられ、本殿などの建築や、神の像はつくらず、自然のままの依り代を拝んでいました。その形が現在まで続いているのが三輪山を御…

仏教伝来以前の古い日本では、神は山、滝、岩や樹木等に宿ると信じられ、本殿などの建築や、神の像はつくらず、自然のままの依り代を拝んでいました。その形が現在まで続いているのが三輪山を御…

国宝「鳥獣戯画」は、誰もが一度は目にしたことのある、日本絵画史上もっとも有名な作品の一つです。本展では、擬人化した動物たちや人びとの営みを墨一色で躍動的に描いた甲・乙・丙・丁全4巻…

奈良・斑鳩の地に悠久の歴史を刻む法隆寺は、推古天皇15年(607)、聖徳太子によって創建されたと伝えられます。太子は仏教の真理を深く追求し、また冠位十二階や憲法十七条などの制度…

鑑真 (がんじん 688~763)は、中国・唐時代の高僧で、律の大家として尊敬を集めました。 しかし、日本での戒律の整備を目指していた聖武天皇の意を受けた日本僧・栄叡(ようえい)、…
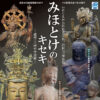
かつて遠江国に属した浜松市、袋井市、湖西市と、三河国に属した豊橋市は、浜名湖を中心とした文化的なつながりを形成してきました。都から伝播した仏教文化もこの地域に根付き、現在も平安時代…

利休七哲とは、蒲生氏郷、細川三斎(忠興)、高山右近、古田織部など、利休の武家の弟子七人を指す言葉です。かつて前田利長(利家の子)も数えられていました。今回の企画展では、三斎・右近…
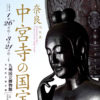
斑鳩の地で尼寺として創建された中宮寺。その当初の伽藍の様子や、紡つむがれてきた歴史、聖徳太子との深いつながりを示します。鎌倉時代には尼僧信如しんにょが天寿国繍帳を再発見し、寺を再興…
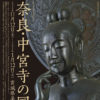
奈良・斑鳩の法隆寺の東に位置する中宮寺は、聖徳太子の御母・穴穂部間人皇后(あなほべのはしひとこうごう)崩御の後、その住まいを聖徳太子が寺院にされたと伝わります。鎌倉時代の信如(しん…
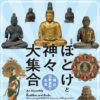
岡山県は、古代には「吉備国」と呼ばれ、大和や出雲に並ぶ一大勢力を築いていたことが知られています。その歴史を背景に、岡山県では古くから宗教文化が豊かに育まれてきました。密教や浄土信…
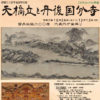
本年、当館は、昭和45(1970)年11月7日の開館から50周年を迎えます。当館の建設に先立って、国史跡・丹後国分寺跡を含めて用地が購入され、史跡の環境整備と資料館の建設工事が相…