
特集展示「筑紫の神と仏」
九州国立博物館開館15周年・大宰府史跡指定100年を記念し、特集展示「筑紫の神と仏」を開催いたします。本展は九州国立博物館が平成17年(2005)の開館以来実施してきた、大宰府学研…

九州国立博物館開館15周年・大宰府史跡指定100年を記念し、特集展示「筑紫の神と仏」を開催いたします。本展は九州国立博物館が平成17年(2005)の開館以来実施してきた、大宰府学研…

西国三十三所は、閻魔大王のお告げを受けた大和国長谷寺の開基・徳道上人が人々を救うために定めたと伝わる33の観音霊場を巡る、日本最古の巡礼路です。 巡礼路の総距離は約1000キ…
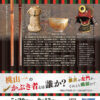
関ヶ原合戦の後、世が落ち着きつつあった17世紀初頭、「かぶき者」と呼ばれる人たちが出現しました。彼らは異様な風体をし、常軌を逸した行動で知られる存在でした。その「第一」といわれた…
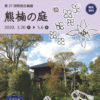
登録有形文化財「旧南方家住宅」(南方熊楠邸)は、南方熊楠が1916(大正5)年から亡くなるまでの25年間を過ごした邸宅です。敷地内の広い庭は、熊楠にとって重要な植栽、観察、研究の場…

千利休亡き後、秀吉によって「天下一」の茶人に指名されたのは古田織部でした。後に織部は、徳川二代将軍秀忠の茶の湯指南役となり、茶会の式法などを整備していきます。同時に「へうけもの」…

18世紀の上方の画壇は、狩野派、土佐派、文人画派、長崎派、円山派など、文字通り多士済々の様相を呈していました。中でも、円山応挙(1733-1795)の写生画は京都で大流行します。そ…

四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)は、須弥山世界の四方にいて、仏教世界や仏法を守るカミです。このうち北方を守護する多聞天は、「毘沙門天」の名で単独の像としても造像、信仰され…
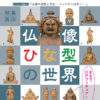
仏像などの彫刻をつくる際、仏師たちは「雛型」と呼ばれる模型を使用しました。大きな仏像をどのようにして効率的に彫るかを考えるため、または注文主である施主や発願者にみせる完成予想図と…

われわれのご先祖さまは、神さまをどのような姿と考えていたのでしょうか。今にのこる神々の像は、貴族のような姿のものあり、甲冑をまとって怒りの表情のものあり。さまざまな姿をしています。…
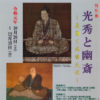
来年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公明智光秀と、その盟友細川幽斎(藤孝)は武将の中でも特に教養の高い文化人でした。光秀が本能寺の変直前に愛宕山で百韻連歌を催したことや、幽…