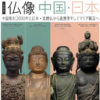
特別展「仏像 中国・日本」
悠久の歴史を刻む中国の仏像。それを受容してきた日本の視点で設み解きながら通観する展覧会です。日本にはいつの時代にも中国でつくられた多くの仏像や仏画がもたらされ、日本の仏像のすがたに…
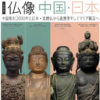
悠久の歴史を刻む中国の仏像。それを受容してきた日本の視点で設み解きながら通観する展覧会です。日本にはいつの時代にも中国でつくられた多くの仏像や仏画がもたらされ、日本の仏像のすがたに…
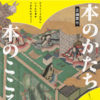
世界にも稀な伝存量と種類の多様さを誇る日本の古典籍――その豊かな広がりを原本の展示によって紹介します。 表記、レイアウト、挿絵などさまざまな面に光を当てながら特色を紹介するととも…

今回の展示では、ICOM国際博物館会議in京都に合わせ、新発見の本阿弥光悦作 色替り赤筒茶碗 銘「有明」のほか、朝鮮出兵持帰の虎の頭蓋骨、蜂須賀家伝来 長次郎作 赤茶碗、玄悦御本釘…
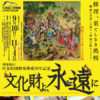
文化財を未来につなぐ 形あるものは全て、永遠にその姿を保つことはできません。木や漆、絹などの脆弱な素材で造られたものが多い文化財は、ときどきに施された修理によって今日まで伝えら…

世界遺産鬪雞神社は、南方熊楠顕彰館・南方熊楠邸から徒歩10分程のところにあります。 熊楠にとっての鬪雞神社とは、フィールドワークの場であり、また妻(松枝)の実家でもありました。朝…

8世紀半ば、聖武天皇によって甲賀の地に紫香楽宮が造営され、大仏の造像が発願されました。しかし、紫香楽宮は短期のうちに造営が中止され、発願された大仏も、還都された平城京で造営され、現…
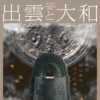
令和2年(2020)は、我が国最古の正史『日本書紀』が編纂された養老4年(720)から1300年という記念すべき年です。その冒頭に記された国譲り神話によると、出雲大社に鎮座するオオ…
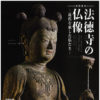
法徳寺は、奈良市十輪院町に位置する融通念仏宗の寺院です。本尊は平安時代後期にさかのぼる阿弥陀如来立像ですが、本展で注目するのは近年この寺に寄進された約30軀の仏像です。これらは、…

奈良県北東部に所在する岡寺、室生寺、長谷寺、安倍文殊院の四寺は、いずれも7〜8世紀に創建された古刹で、きわめて魅力に富んだ仏像を伝えています。奈良時代に流行した木心乾漆造の岡寺・義…
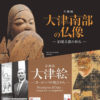
大津市の瀬田川から東の地域は、かつて栗太郡と呼ばれていました。その栗太郡は現在の草津市や栗東市、守山市の一部も含んでいます。この地域には田上山や金勝山など著名な霊峰があり、古代か…