
秋期企画展「秩父を散歩しませんか? 神社仏閣に地形と石を訪ねる」
荒川の上流域には、地形・地質を特徴づけるジオパーク秩父があります。ジオサイトと呼ばれる観察ポイントの中には神社や仏閣の境内となっている場所が多数あるので、本展示では、神社仏閣の境内…

荒川の上流域には、地形・地質を特徴づけるジオパーク秩父があります。ジオサイトと呼ばれる観察ポイントの中には神社や仏閣の境内となっている場所が多数あるので、本展示では、神社仏閣の境内…

インドで生まれ、中国大陸、朝鮮半島を経て日本列島に伝来した仏教は、やがてこの地の、緑深い山々や、苔むす巨岩に降り立つ神々と融合して、人々の信仰世界を彩り豊かなものにしていきました…
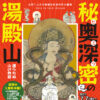
古くから山岳信仰の霊場として栄えてきた出羽三山。 中でも湯殿山は三山の奥の院(もっとも重要な場所)であり、その神秘さゆえに「語るなかれ、聞くなかれ」といわれるほど篤く信仰されてい…

釈迦仏入滅。この暗く沈んだ世界に救世の光をもたらす未来仏・弥勒。東アジアで広く親しまれ、日本に深く浸透した弥勒は誕生の地ガンダーラから時空を超え、交易と仏教伝来の道シルクロードを…

仏像を前にしたとき、そのすがた、かたちがどのようなものか、まずはみつめることから始まります。 それは「ほとけの心」に触れることです。 市内屈指の古像である蓮花寺・地蔵菩薩立像は…

「天下三宗匠」とは、織田信長・豊臣秀吉に仕えた今井宗久・津田(天王寺屋)宗及・千利休の堺の三人の茶人を表します。本展ではそのゆかりのものと、利休高弟の山上宗二、嫡男の道安(紹安)、…
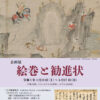
現在のアニメーションのルーツとも言われる絵巻物は、巻物を開きながら読み進めることによって描かれた場面の時間が経過する、物語や由緒を伝えるのに適した絵画形式のひとつです。中世から近…

令和4年(2022)、聖徳太子が没して1400年目を迎えます。そこで、その生涯をたとり、没後の聖徳太子信仰の広がりを紹介する展覧会を開催します。聖徳太子(574~622)は用明天…
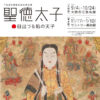
聖徳太子(574~622)は、推古天皇の摂政となり国の礎を築く一方で、仏教を篤く信奉し、日本の仏教の出発点となった人物です。後世には聖徳太子への信仰が生まれ、諸宗派の名だたる高僧、…

西暦622年に聖徳太子(574~622)がお亡くなりになってから、1400年遠忌という記念の年、奈良国立博物館と東京国立博物館では聖徳太子の偉業と法隆寺の美術を紹介する特別展を開催…